いよいよ本当に「おごれる者も久しからず」になってきた「新・平家物語」。
頼朝と義経は対面して、源氏軍も大きくなってきました。
もう一つの源氏軍、木曾義仲率いる一軍も活気を成してきました。
それなのに、肝心の平家方と言えば。
平清盛はいよいよ死んでしまい、平家の総領は若干37歳の宗盛。その他の平家の公達は若いのです。そのうえ、すっかり平和に慣れ、公家生活に慣れ、およそ戦には向かない。
一方、源氏方はというと、頼朝軍と木曾軍同士でにらみをきかしていたり、頼朝軍の中でも不仲が生じていて、そこまで大きな動きはないといえばない。
でも木曾軍は、大将の木曾義仲をはじめ、猛者が集まっている。なにせ、北の方の巴御前、愛人の葵御前も立派な女武者なのです。
私はなんといっても、この木曾軍が一番好きです。女にすぐなびく義仲、嫉妬しあう巴御前と葵御前、と人間関係はどろどろしていますが、美青年の義仲の両脇に美しい女武者二人、という図が美しすぎる・・・
と戯言はこの辺で、引用ダイジェストを。
やっぱり吉川英治。文章がかっこいいわ・・・
(清盛が頼朝軍の挙兵を聞いて悪夢にうなされつつ、自分の所業を思い起こすシーンにて)
「しかし、おれにも、いい分はある」
p105
・・・(中略)・・・
「院政の弊害は久しいことだ。・・・(中略)・・・おれが天魔外道なら、法皇は大魔王だろう。何ゆえ、おればかりを世は責めるのか。—稀代な魔王を降伏せしめるには、稀代な外道にならねばできぬ。・・・・・・・おう、憎まば憎め、清盛の今は、むかし、日吉山王(ひえさんのう)の神輿へ矢を放ったあのおりの心と違っていない」
自分の声で、夢がさめる。
和田ヶ崎の松風と浪音が、夜は、雪ノ御所の深くまで、とどろに聞こえていた。
むかし、かれが神輿に矢を射たときは、民衆の石の雨が、かれに加勢して、山法師と闘った。
けれで、清盛が今日、つがえている矢には、一門のほか、味方がない。民衆の石は、かえって、清盛へ降りそそがれている。
(かつては源義朝に仕え、没後には平家の禄を食んできた斎藤別当実盛。その実盛の元へ、源氏のもとへ戻ろう、という誘いが来る)
「では、実盛どのには、このまま都に居残るおつもりか」
p112
「いや、てまえも東国へ立つことは立つが、主命やむなく、維盛卿の軍に従いて参らにゃならぬ」
「えっ、佐殿を敵にまわして」
「されば、なんの能もない老後の二十年を養われて来た恩も思われ、今さら平家に裏切りもでき申さぬ。あわれ、御帰国の後、武蔵七党の友輩が、なぜ実盛はきょうの御旗の下に見えぬぞ—と問うたなら、実盛の心底はかくのごとしと、嗤うておくりやれ」
「余人ならぬ御辺のこと。よくよくなお覚悟ではあろう。嗤うどころか、聞く身も辛うござる」
・・・(中略)・・・
それから三人は、淋しい一夕の酒をともにした。あすは敵味方、永遠の別杯となるかもしれない。しかし、おたがいの立場と、考え方は、自由であった。充分理解し合える仲の友でもあった。
この潔い実盛は、かつて自分がその命を救った、義仲の軍と対面することになり、自ら討たれるのであった。
頼朝とせっかく対面したのに、頼朝に冷たくあしらわれる義経。ついに、自分を慕ってついてきてくれた部下とも離れ離れにされてしまった(頼朝は、義経を慕ってきた、というのに快く思わなかったらしい)
九郎殿山は、急にさびしい。義経は、馬にさえ盲愛を感じるたちである。人への愛執が人いちばい強い。部下とでも、そうだった。人の世のうちで、もっとも辛いことのように、別離を淋しがる。
p147
そうしたところへ、ある日、この九郎殿山へ、一個の大法師が、旅草鞋(たびわらんじ)を踏みしめ、身にふさわしい大薙刀を片手に、ゆらりと訪ねて来て、
「これは、都の仁王小路に潜み、久しく、君のお便りをお待ちこがれていた武蔵坊弁慶でおざる。かく、鎌倉まで下られながら、何ゆえ、弁慶には、一片のお便りも賜わらぬにや。—お恨みを申しに参ったりと、お取次ぎありたい。かつての、主従のおちかいは、そも、一時のおん戯れか否か。—弁慶でおざる。弁慶参ったと、わが君へ、ご披露なありたい」
と、仮屋の門へ向かって、どなっていた。
今回も麻鳥の出番があった。もしかしたらこの本の中で一番好きなキャラかも。その麻鳥は医者となって貧民を救い、その腕をかわれて平清盛を看ることとなる。
結局清盛は死に、麻鳥はそのまま姿を消すが、平家軍が北上する際、平家の公達の一人、皇后宮亮経正(こうごうぐうのすけつねまさ)が竹生島(ちくぶじま)に立ち寄った時。ちなみに経正は琵琶の名手(能にもあったはず)、禰宜に竹生島の社に伝わる琵琶”仙堂”で一曲請われる。それを
「幼少より、琵琶は好むものだが、さりとて、仙童を弾じるほどな技能はない。・・・・・・それよりもこの静かなる鳰の湖(におのうみ)に、まなこを半眼にし、耳を澄ましていたがよい。—暮れかかる雲も何やらん歌うているげな。—波のささやき、松風のことば、あらゆるものが天楽の奏でであろうが。なんで、この自然の音楽をよに、経正が下手な琵琶などを、妙音天女も聞こし召そうや」
p333
と断った後に、麻鳥にばったり会うのだった(禰宜は麻鳥の叔父))
「…(中略)・・・それにしても、御辺のごとき名医が、どうして、施薬院の官職も賜らず、貧しい町の片隅に朽ちているのか」
「いえ、どういたしました、わたくしはべつに貧しいことはございません」
麻鳥は、すまして答えた。
それ以上は、笑って何も答えない。・・・(中略)・・・
経正は、・・・(中略)・・・一そう麻鳥をゆかしく思った。そして、何を好んで貧乏しているかといった自分の問いに「決して、わたくしは、貧しくない」と答えて、目(旧字)を上げたりときのその目(旧字)を、もう一度、思い出して恥ずかしくなった。・・・(中略)・・・
経正は、眼のまえの一個の男に、なんともいえない気高さと、生の強さを、見るのであった。
世の波騒(なみざい)も、権力も、毀誉(きよ)も褒貶(ほうへん)も、栄華も、麻鳥には、なんのかかわりもない。どんなに血みどろを好む魔物でも、彼の無欲と愛情に徹した姿を、血の池へ追いこむことはできないであろう。
経正は、心のうちで、ほっと嘆息をもらした。この男に与える物。いつかの礼ぞ、といって、与えるような物を—自分は何も持ち合わせていないと思った。
麻鳥は、心の王者。自分は、心の貧者であった。・・・(中略)・・・
「そうだ」
経正は、禰宜をふりかえりみて、ふといった。
「宝器をけがす畏れはあるが、さきにおはなしの”仙童”をお貸し給わるまいか」
・・・(中略)・・・
経正は、両手で琵琶をうけて拝した。そして、琵琶のかすかな埃を、鎧下着の袖で、そっとふいた。
「麻鳥—」と、あらたまって、経正は、辞を低うしていった。
・・・(中略)・・・
「・・・(中略)・・・したが、御辺の生涯を承っては、何やら、礼物などもさし出しかねるが」
「もとより、そのような物戴こうとは、思いもよりません」
「・・・・・・が、貧者の一燈と申すこともあれば、経正が心をこめて一曲を弾じよう。礼というにはあらねど、所は竹生島、また、今生の一期やも分からぬ。聞いてくれるであろうか」
やたら麻鳥のシーンが長くなってしまいましたが、本当にこのシーンはいい!この後の、琵琶を奏でるところといい・・・
麻鳥には最後まで出て来て欲しいです。
(吉川英治 「吉川英治全集35 新・平家物語」 講談社 1981年)
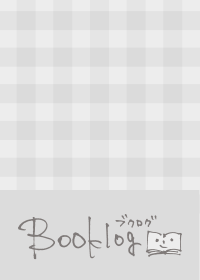

コメント